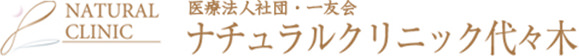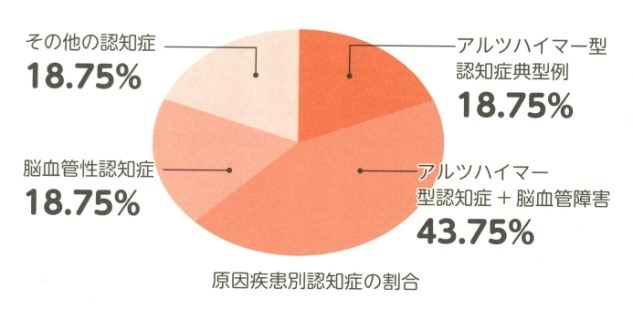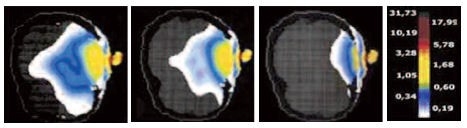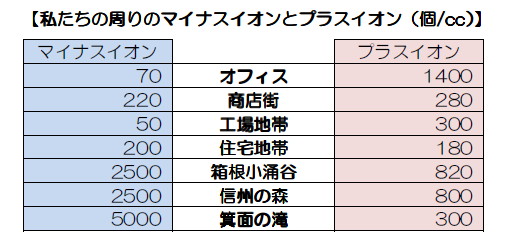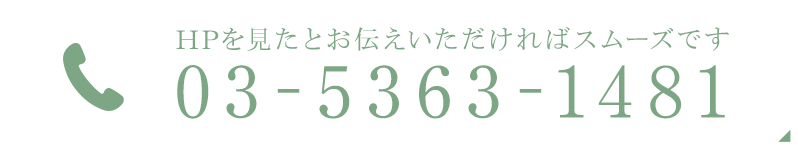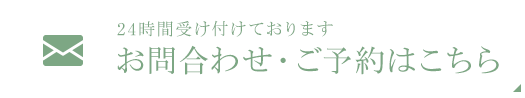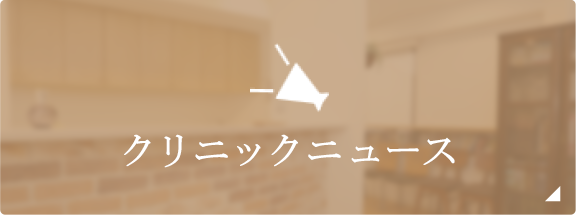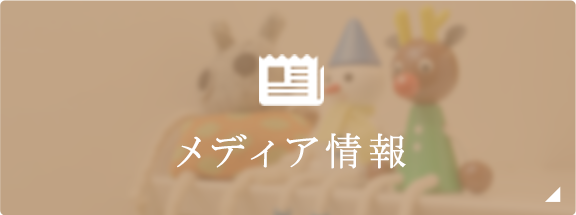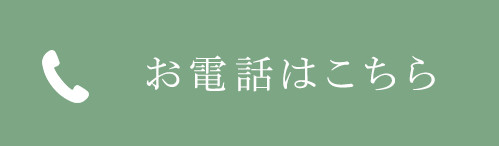一生で6億から7億回も行う「呼吸」。私たちは普段、無意識の中で息をしていますが、呼吸の仕方で心と身体の健康も大きく左右されます。イライラや不安、焦っている時には呼吸がいつの間にか浅くなっています。呼吸が浅いとストレスが増え、肺の一部しか酸素が届けられないため、血液中の酸素が不足し、身体にダメージを与えます。特にダメージが大きいのが酸素を最も必要とする「脳」と言われています。
【実践№1深呼吸をするように心がける】
深くゆっくりと息をすると、リラックス時に働く副交感神経がスムーズに働き、ホルモン分泌や免疫の働きが正常になります。逆に浅い呼吸は、緊張した時に動き出す交感神経ばかりが働いてしまいます。
-浅い呼吸が招く主な病気-
ストレス病(精神的疾患を含)、自律神経失調症、呼吸関連筋肉群の凝り、背骨のゆがみ、
胃や内臓・肋骨の下垂、肝機能の低下、便秘、呼吸器系疾患
【実践№2 鼻呼吸を意識して】
鼻呼吸は外界から入ってくる異物を排除する働きがあります。口呼吸では排気ガスやほこり、チリなどが直接肺に入ってしまい、風邪やアレルギーにもかかりやすくなります。
-口呼吸チェック-
○起床時、喉がヒリヒリする
○音を立てて食べる ○唇がカサカサしている
○夢中な時口が開く ○いびきをかく
【実践№3 腹式呼吸にチャレンジ】
深くゆっくり呼吸をするためには「腹式呼吸」がお勧めです。
①ゆっくりと口から息を吐く。身体の中の空気を全て外に出すイメージで、時間をかけて吐き出します。この時、お腹が徐々に引っ込むように気をつけます。十分に吐き切ったところで更に「フーフー」と残りの息を出しましょう。
②鼻から深く息を吸います。この時に下腹が膨らむように意識します。
③再び口から息を吐きます。吸った時よりも2倍程度時間をかけるつもりで長くゆっくりと吐き出します。
④この動作の呼吸を一日に数回繰り返します。起床時、就寝前など時間を決めると良いです。
-腹式呼吸法による作用-
・心の乱れを整え、感情もコントロールできる ・血液循環の改善 ・老廃物の浄化
・免疫力の向上 ・太りにくい体質になる ・むくみの改善 ・便秘の改善 etc
ナチュラルクリニック代々木 ※クリニックニュース Vol.14 掲載記事